🪐 水星の1日は1年より長いってホント?

地球では「1日=24時間」「1年=365日」が当たり前ですよね。
でも、太陽に最も近い惑星・水星では、その常識が通用しないのです。
なんと水星では、「1日」が「1年」よりも長いという、ちょっと信じがたい現象が起きています。
でもこれは、まぎれもない事実。
地球とはまったくちがう「時間の感覚」が、水星には流れているんです。
では、なぜそんなことになるのでしょうか?
この記事では、水星の自転と公転のリズムに注目しながら、この不思議な現象の理由をやさしく解説していきます。
🔄 まずは「自転」と「公転」の違いから

この現象を理解するには、まず「自転」と「公転」について整理しておくことが大切です。
-
自転:惑星が自分自身の軸を中心に回る動き
-
公転:惑星が太陽のまわりを回る動き
地球では、自転が1回=1日(24時間)、公転が1周=1年(365日)にあたります。
毎日、太陽が昇って沈むのは自転のためで、季節が変わるのは公転によるものですね。
ところが水星では、この自転と公転のバランスがとても特殊なのです。
☄️ 水星の1年はたった88日!
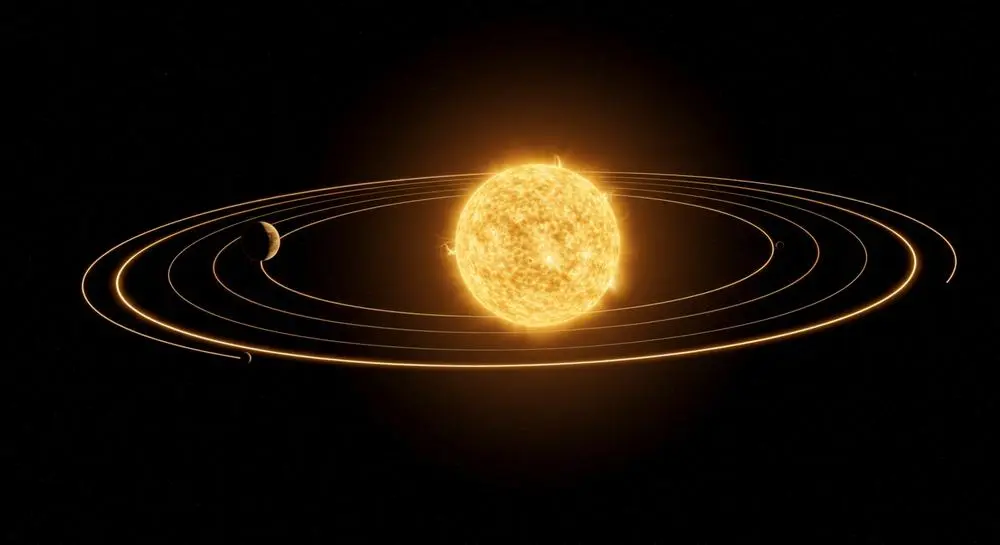
水星は太陽にいちばん近い場所を回っているため、公転のスピードがとても速いのが特徴です。
太陽のまわりを1周するのにかかる時間は、たったの約88日。
つまり水星の「1年」は、地球の約4分の1。
カレンダーがあるとしたら、3か月で1年が終わるということになります。
🕒 でも1日はなんと約176日!
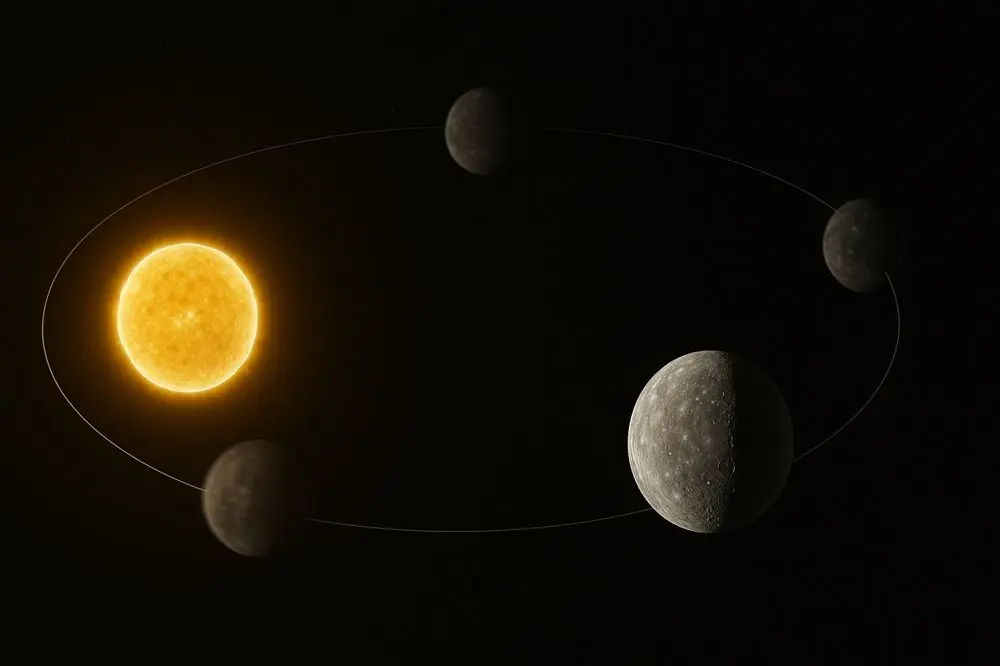
では、水星の「1日」はどれくらいの長さなのでしょうか?
水星は1回自転するのに約59日もかかる、ゆっくりとした回転の星です。
しかし、ここで重要なのが「太陽日(たいようじつ)」という考え方です。
太陽日とは、太陽が再び同じ場所に昇ってくるまでの時間のこと。
水星ではこの太陽日が約176日もかかるのです。
つまり、水星では「1日=176日」であり、
太陽が昇ってから、また昇るまでに半年近くかかるというわけです。
⚖️ なぜそんな現象が起きるの?

この不思議な時間感覚の理由は、水星の自転と公転の比率が「3:2」でつり合っていることにあります。
どういうことかというと、水星は公転を2回(88日×2=176日)するあいだに、
自転を3回(59日×3=177日)行うというリズムになっています。
このように、自転と公転が一定の比率で重なっている状態を、「スピンオービット共鳴」といいます。
この共鳴によって、太陽が再び同じ場所に戻ってくるには約176日かかることになり、
結果として、「1日が1年よりも長い」という現象が生まれているのです。
この共鳴関係は、重力や潮汐の影響によって自然に形成されたと考えられています。
とても精密で、不思議なバランスで成り立っているのです。
🔥❄️ 水星では昼と夜が超ロングタイム!

水星では「1日=176日」ということは、
昼と夜もそれぞれ88日ずつという、信じられない長さになります。
-
昼:太陽が出ている時間 → 約88日間も続く
-
夜:太陽が沈んでいる時間 → 約88日間の暗闇が続く
こんな極端な昼と夜の繰り返しは、地球では想像できませんよね。
さらに、水星には大気がほとんどないため、昼と夜の温度差がとても激しいのです。
-
昼の最高気温:約430℃の灼熱(しゃくねつ)
-
夜の最低気温:約−180℃の極寒(きょくかん)
なんと、その差は600℃以上にもなります。
こんな長時間、太陽に焼かれたり、凍りつくような寒さが続いたりする環境では、
生き物が生き残るのは、まず不可能に近いと言えるでしょう。
✨ まとめ:水星は時間感覚がちがう惑星
-
水星の「1年」は88日
-
水星の「1日(太陽日)」は176日
-
つまり、1日が1年より長い
-
原因は「自転:公転=3:2」という共鳴リズム
-
昼と夜が長く、温度差はなんと600℃以上!
私たちが当たり前だと思っている「時間」も、
宇宙の他の場所では、まったく違うルールで流れているのです。
空の向こうで、ゆっくりと時を刻む水星。
その静かなリズムは、宇宙の奥深さと不思議さを、静かに語りかけてくれているようです。
🌕 人気記事の一部をご紹介!
🔸 月は地球のかけらだった? ジャイアントインパクト説をやさしく解説
🔸 月の裏側には何がある? 見えない理由と不思議をやさしく解説
宇宙動画はRiddScope公式チャンネルで公開中!



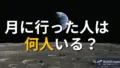
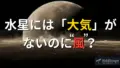
コメント